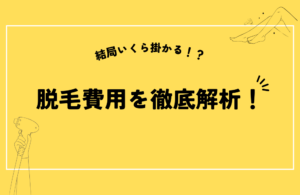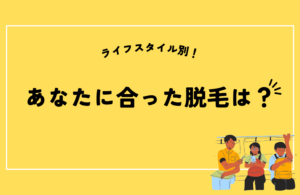脱毛スタッフが知っている毛の知識
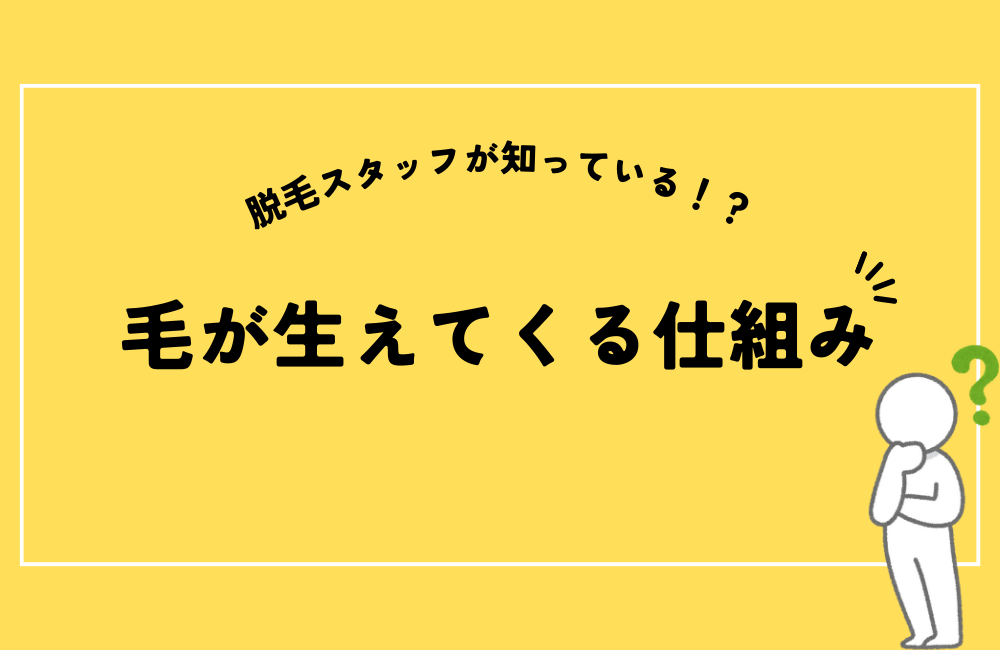
毛が生えてくる仕組み
人間の体には、頭髪や眉毛、まつ毛、体毛などさまざまな種類の毛が存在します。これらの毛はすべて「毛包(もうほう)」と呼ばれる皮膚の構造から生えており、その成長には非常に複雑で精密な生理的プロセスが関与しています。毛が生えてくる仕組みは、主に「毛周期(ヘアサイクル)」というサイクルを通じて制御されており、遺伝やホルモン、栄養、年齢などさまざまな要因の影響を受けています。
毛包の構造と役割
毛は「毛包」と呼ばれる皮膚のくぼみの中で作られます。毛包は、皮膚の表皮から真皮、さらには皮下組織にまで伸びており、毛根と毛乳頭(もうにゅうとう)という組織を内部に含んでいます。毛乳頭は毛包の最も深い部分に位置し、多数の毛細血管が集まる場所で、毛母細胞(もうぼさいぼう)に栄養や酸素を供給する役割を果たします。
毛母細胞は分裂能力の高い細胞であり、この細胞が活発に分裂し、角化(かくか)というプロセスを経て硬くなり、毛幹(もうかん)となって皮膚表面に押し出されていくことで、毛が「生えている」ように見えるのです。
毛周期(ヘアサイクル)
毛の成長は一貫して続いているわけではなく、「成長期」「退行期」「休止期」という3つの段階からなる毛周期によって制御されています。
- 成長期(アナゲン期)
毛母細胞が活発に分裂して毛が伸びる時期。頭髪ではこの期間が2〜6年続くと言われており、全体の約80〜90%の毛がこの段階にあります。 - 退行期(カタゲン期)
毛母細胞の活動が停止し、毛乳頭と毛根の接触が途切れることで毛の成長が止まります。約2〜3週間の短い期間で、全体の約1%がこの段階にあります。 - 休止期(テロゲン期)
成長を終えた毛が毛包の中で静止し、やがて自然に抜け落ちる準備をする段階。約3〜4か月続き、全体の10〜15%の毛がこの段階にあります。毛が抜けた後、毛包は再び新たな成長期に入り、次の毛が作られます。
このサイクルは一生を通じて繰り返されており、私たちが日々抜け毛を見るのは、休止期に入った毛が自然に脱落している現象です。
ホルモンと毛の関係
毛の成長にはホルモンが密接に関わっています。特に、男性ホルモンである「テストステロン」およびその代謝産物「ジヒドロテストステロン(DHT)」は、体毛やひげの成長を促進する一方で、頭髪に対しては成長を妨げる作用があります。これが、男性型脱毛症(AGA)の原因となります。
また、女性ホルモンである「エストロゲン」は、毛周期の成長期を延ばす働きがあり、頭髪の成長を維持するのに重要です。出産後や更年期にエストロゲンが急激に減少すると、抜け毛が増える原因となることもあります。
栄養と血行の影響
毛母細胞の活性には、十分な栄養と酸素の供給が欠かせません。ビタミンB群、亜鉛、鉄分、たんぱく質などの栄養素が不足すると、毛の成長が妨げられたり、脱毛が進行したりすることがあります。また、頭皮の血行が悪くなると、毛乳頭への栄養供給が滞り、毛母細胞の働きが弱くなるため、冷え性や肩こり、ストレスなども間接的に影響します。
遺伝と年齢の影響
毛の太さや量、成長速度などは遺伝的要因に強く影響されます。特にAGA(男性型脱毛症)は遺伝との関係が深いとされており、親族に脱毛傾向がある場合、発症リスクが高まります。
また、加齢に伴って毛周期の成長期が短くなり、休止期が長くなる傾向があります。これにより、毛が細くなったり、本数が減ったりする「老化性脱毛」が進行します。
まとめ
毛が生えてくる仕組みは、毛包内の毛母細胞の分裂と成長によって成り立っており、それは「毛周期」というサイクルによって制御されています。このプロセスには、ホルモンや栄養、血流、遺伝、年齢など多くの要因が関与しており、どれか一つのバランスが崩れるだけでも毛の状態に変化が生じます。毛の健康を保つためには、日々の生活習慣やストレス管理、栄養バランスの取れた食事が重要です。
ムダ毛が気になる。というお客様向けに無料相談も常時開催しているのでお気軽にご相談下さい!